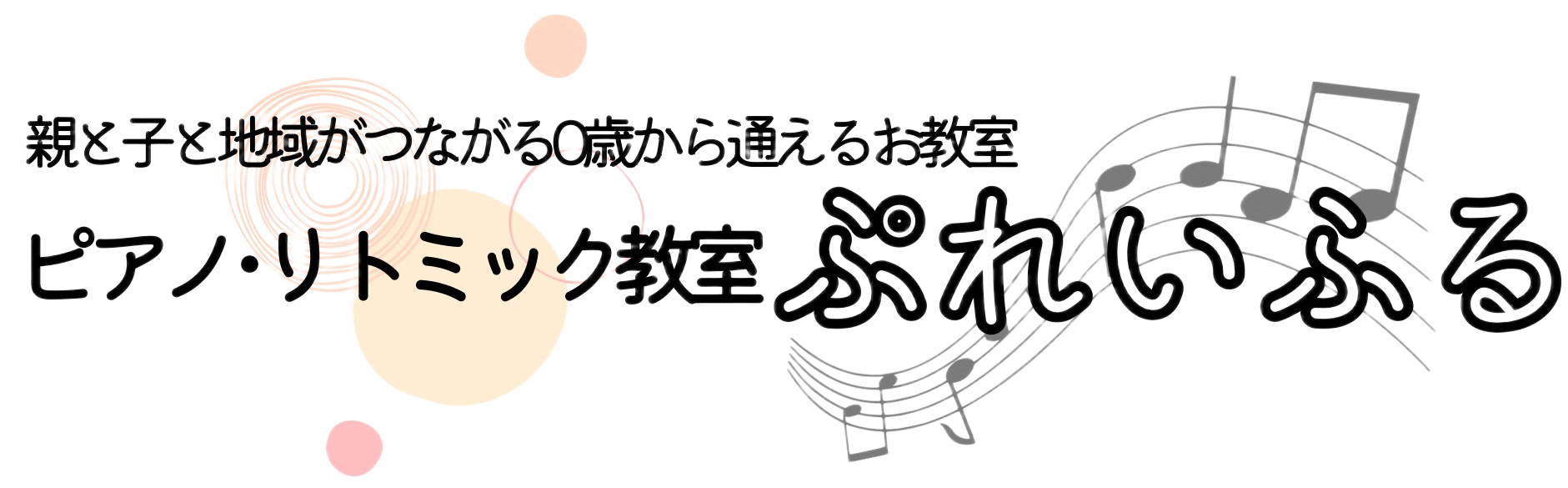国際子ども図書館 児童文学連続講座
1月上旬頃のこと、上野の国際子ども図書館へ行きました。
惚れ惚れするような荘厳な建築に集められた蔵書の数々。
ただただ読み聞かせをして過ごした1日。
静かに流れる時間をゆったりと味わう贅沢なひと時でした。


明治から現代までの児童書(児童文学と絵本)の流れを追うことのできる常設展示室の児童書ギャラリーでは、寺村輝雄の王様シリーズの第1作目
「 ぞうのたまごのたまごやき 」が初出された1956年の「こどものとも」を見ることができました。
つい先日義実家にある長新太さん挿絵版の絵本で姉妹に読み聞かせをしたばかりだったので、子どもたちにとってもタイムリーな出会いとなりました。
そのほか長女の大好きなバージニア・リー・バートンの「ちいさいおうち」の出版当初は縦書きだった実際の絵本も手に取って見ることができました。
これらを始め貴重な絵本や児童書を実際に手に取って読むことができる素晴らしい展示室でした。
約1万冊の児童書が収められている“こどものへや”ではすっかり長居してしまい、長女はエルサ・ベスコフの美しい絵本に魅力されていました。
年末に国際子ども図書館主催の幼年童話の講座をアーカイブ配信で聴講してから、文字ではなく「声」によって紡がれる子どもの物語の世界をいま一度大切にしたいと考えるようになりました。
小学校低学年頃までの子どもは文字が読めていたとしても、文字からの認識よりも声から聞く方が文脈を捉え、理解し、想像を膨らませることができる。
その読み聞かせる声が「聞くためのコップ」に注がれていくことで国語力の土台が育まれ、そしてコップがたっぷりと満たされた時に自立した読者となるのではないかということでした。
つまりそれは「文字が読める」ということだけではなくて、文字を通して文脈を捉え、情景を思い浮かべ、自分なりの考察ができるということ。
音楽においてリトミックが楽譜の世界への架け橋となることにも通ずることだし、私自身も大切にしていたはずだったのですが長女が文字が読めるようになり、一人読みがスムーズにできるようになるにつれて、自然と読み聞かせの時間が少なくなっていたので、ここ最近は一人読みに夢中になっている長女にも、読み聞かせの時間を作るように意識しています。
子どもが「読んで」と言ってくるうちは、まだまだコップに声を注ぐ時期だと思います。
エルマーシリーズやゾロリシリーズを「読んで」と持ってきた時には、「え…」と思ってしまうのが本音ですが。
それでも求められる限りはそれに応えたい。
親の役目は、「本を1人で読めるようにすること」ではなく「物語を自分なりに楽しめるようにすること」のサポート。
同じようで、その根本は全く違うことだと思っています。
言葉は文字である前に「声」であって、体温を持っているものだからこそ、ふれあいと同じくらい、大切にしたいと思うのです。